 教員志望の方
教員志望の方一度企業に就職したけれど、やっぱり先生になりたい気持ちがある‥



第二新卒で教員って、実際どうなんだろう?新卒よりもやっぱり不利なのかな?
「第二新卒で教員になるって、実際のところどうなの?やめておいた方がいいの?」と漠然としたお悩みをお持ちではないですか?
実は第二新卒で教員をめざす方も多くいらっしゃいますし、第二新卒でも条件によっては「新卒」と同じように内定を出して受け入れている学校もあります。
この記事では、第二新卒で教員になるメリットとデメリットを、私立学校での人事担当経験を基に徹底的に解説していきます!
~自己紹介~
私は教員一家に生まれ、両親・叔父叔母・祖父はみんな公立小中高の先生。そして自身は英会話講師 → 私立高校で教員 → 今は教育関連企業で会社員しています。
教育業界で10年。そのうち8年間は人事を担当。教育業界での採用や転職に長く関わってきました。その経験をもとに、記事を書いています。
この記事を読むと分かること
- 第二新卒で教員をめざすメリットとデメリット
- 第二新卒に対して、人事担当者が抱くリアルな印象
- 第二新卒の方が教員をめざすなら、私立学校がオススメな理由
最後まで読んでいただき、第二新卒で教員になる夢を実現させる参考にしていただければ幸いです!
第二新卒ってどんな人?転職市場における立ち位置


第二新卒の定義
まずはじめに「第二新卒」という言葉について、改めて確認しておきましょう。
第二新卒という言葉に法的なものなどハッキリとした定義はありません。一般的には「新卒で入社してから3年以内のビジネスパーソン」を指すことが多いようです。新卒で入社した会社を1~3年で退職し、新しい仕事を探している人が該当します。
マイナビ転職/第二新卒とは



え!決まってないの?知らなかった!
明確な定義はありませんが、「社会人として就業経験があり」「新卒で入社した企業を1~3年で辞めている」という状況が「第二新卒」となります。



うちの学校でも「社会人経験2年までの方は、第二新卒にしましょう!」と決めて、受け入れをしていました。
企業の人事担当の視点からすると、第二新卒の市場はとても大きく、人としても非常に魅力的です。
その理由は
- 社会人としての基本的なマナーを身につけている
- 実社会での就業経験がある(仕事の進め方が分かっている)
という点で、ポテンシャルの高さを感じています。
新卒採用とは異なり、第二新卒はある程度の社会経験を踏まえているので、「今後活躍してくれる若さ」と「即戦力として期待できる」という両方の魅力を持っています。
では「第二新卒として教員になりたい!」という方に向けて、教育現場での状況も紹介します。
第二新卒で教員をめざす理由
では、一度社会に出たみなさんが、改めて教員の道をめざす理由はどんなことがあるでしょうか?
第二新卒で教員をめざす方の、志望理由はこんな感じです。
- 新卒のときの後悔
新卒のときはいろんな理由で教員の道を選ばなかったけど、社会人生活を送りながらも「やっぱり教員になりたかった‥」という気持ちが強い - 企業での経験を通して
企業で働く中で、人が成長することに対して自分がやりがいを持つことを実感したり、社会に貢献する実感を得たいという気持ちが強くなったため、教育という分野に興味を持った - ワークライフバランスの見直し
企業での働き方を通して、自分の生活の中での優先順位が明確になった。長期休暇が取りやすい教員の働き方に魅力を感じるようになった - キャリアチェンジへの意欲
これまでのキャリアで得たスキルや経験を活かしつつ、全く新しい分野で自分の可能性を試したい、専門性を高めたいという意欲がわいた - 社会への貢献意識の高まり
企業活動を通して社会とのかかわりを意識する中で、次世代を育成する形での社会貢献に魅力を感じるようになった
上記の理由以外にも、さまざまな思いを抱えて教員の道をめざす方がいらっしゃると思います。
教員という仕事は確かに大変ですが、それを上回るような「教員にしか感じることができないやりがい」というものがあるのも事実です!
>教員のやりがいについては、コチラの記事も参考にしてください▼
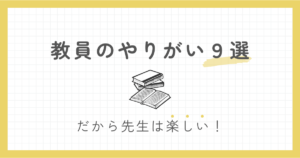
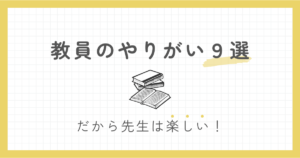
第二新卒で教員をめざすメリット【人事目線】


それではここから、第二新卒で教員をめざすことのメリットを私立学校の人事担当の目線でご紹介していきます!
「第二新卒で教員になるって、実際どうなんだろう?」と不安に思っている方も、ぜひ参考にしてみてください。
第二新卒で教員をめざすことのメリットは、以下の通り。
- 企業での経験を活かして活躍できる
- 若さと吸収力があって、ポテンシャルが高い
- 新鮮な視点と意欲を持っている
1つずつ見ていきましょう!
1.企業での経験を活かして活躍できる
たとえ短い期間であっても、実社会での経験があることは、学校を卒業したばかりの新卒と比べてもとても魅力的です。
例えば、こんな感じで企業での経験を教員としても活かすことができます。
- 社会人としての基礎力:コミュニケーション能力や報連相、スケジュール管理など
➤保護者対応や同僚との連携など、日々の教員の業務を遂行するのに非常に役に立ちます - 多様な視点と柔軟な対応力
➤企業という学校以外の環境での経験を通して、学校の慣習にとらわれない新しい視点を持つことができ、生徒一人ひとりの状況に合わせた柔軟な対応ができるようになります - 保護者や地域社会との連携
➤社会人経験があるからこそ、保護者の方々や地域の方々(いわゆる大人・顧客)とのコミュニケーションもスムーズに進められます - 特定のスキルや知識:ITスキルや語学力など
➤企業で専門的なスキルを身につけることができていれば、それを学校の授業や運営に新しい価値をもたらしてくれる可能性があります
社会人経験(=企業での就職)を経験している教員は比較的少ないので、それを強みとして即戦力として活躍できる可能性が大きいですね!
2.若さと吸収力があって、ポテンシャルが高い
第二新卒は、キャリア転職者(中途)の枠組みで考えると、「若さ」という武器を使えます。
ちなみに、就活において「新卒カード」が一番強いと言われている理由をご存知ですか?
それは【若くて就業経験がない方が、企業に馴染みやすく、一斉に教育ができるから。(今は何もできなくても)育成をすることで、将来貢献してくれる可能性が大きい、ポテンシャルが高いから】なんです。
上記のように、新卒は「今後成長して、活躍してもらえそう」という可能性を信じてもらうことで内定が出されることが多いのですが、第二新卒も同じような印象を与えることができるのです。
その点で非常に有利ですね!
また、若いということは吸収力が高く、新しいスキルやトレンドを取り入れることが得意!という印象を持たれています。
教育現場で言えば、例えば新しい教育手法やICT教育への対応の速さなどは、若い世代ならではの強みです。
3.新鮮な視点と意欲を持っている
第二新卒は、入職後に既存の教員メンバーに新しい風を吹き込んでくれるだろうと期待されている側面もあります。
また、一度企業に就職した背景を持ちながらも「教員として生徒のために貢献したい」という意欲は、周りの教員たちにプラスの影響を与えるでしょう。
「教員一筋で経験を積む」ことも大きな力になりますが、「外の世界を知っていながら教員として活躍する」人材も、学校の中では必要不可欠な存在です!



学校人事としても、第二新卒の方は大歓迎!非常に大きな戦力として期待しています。
第二新卒で教員をめざすデメリットと注意点





第二新卒で教員になるって、メリットばっかりじゃないの?



もちろん、第二新卒で教員をめざすことは、メリットばかりではありません。デメリットも理解して後悔しない転職をしましょう!
それでは、第二新卒で教員をめざすことのデメリットをご紹介していきます。
主に以下の4つです。
- 教員採用試験合格のハードル
- 教員としてのキャリアパスの違いがネックになる
- 企業と学校の働き方のギャップに戸惑う
- 「第二新卒でしょ」という期待が大きい
具体的に1つずつ、見ていきましょう!
1.教員採用試験合格のハードル
学校教員として働くためには、教員免許を取得して採用試験に合格する必要があります。
社会人として日々忙しく働いていながら、教員採用試験を受けていくというのは、とても大変で労力がかかることです。
履歴書などの書類を準備して、採用試験対策を行い、面接を受ける‥という一連の就職活動を、働きながら行うことになるのは、大きなハードルの1つです。
>社会人から教員をめざすことの詳細については、コチラの記事も参考にしてください▼
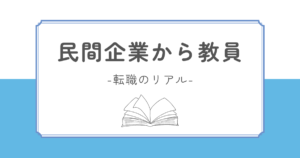
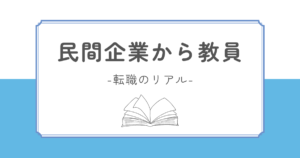
2.教員としてのキャリアパスの違い
学校や自治体によっては、新卒採用の教員と比べて、給与や待遇、研修制度、キャリアアップのルートなどが異なる場合があります。
- 第二新卒と言えどまだ社会人2年目だし、新人研修に出させてほしい
- 新卒で入った先生と、たった2年しか違わないのに、給与がこんなに違うの?
- 教員としての経験は1年しかないのに、新任の子から先輩として頼られちゃう‥
などなど、年齢と教員経験年数がズレることで、不安になることが多くなるかもしれません。
特に公立学校では、まだまだ年功序列や教員の経験年数が重視されるので、その傾向は強くなる可能性があります。
私立学校は、学校によって規定が違うので、志望する学校があれば条件や待遇面をしっかりと確認することをオススメします!
3.企業と学校の働き方のギャップに戸惑う
一定期間、企業で働いた経験がある方にとって、教員の働き方は驚くことが多いかもしれません。
教員の仕事は、授業以外にも部活動や生徒指導、書類作成、保護者対応、学校行事関連などなど、多岐に渡ります。
企業とは違う働き方や、長時間労働になる可能性も理解しておく必要があります。
また、評価制度や目標設定の考え方も企業とは異なることもあるでしょう。
企業で働いた経験を持っているからこそ「え?なんで?」と思うことがあっても、「それが教員の世界だから」とギャップに慣れていくのには時間がかかって大変だということを知っておくと良いでしょう。
4.「第二新卒でしょ」という期待が大きい
第二新卒として転職をすると、「第二新卒でしょ?」という期待が大きくて、プレッシャーを感じることもあるかもしれません。
メリットでご紹介した通り、企業での社会人経験がある第二新卒に対しては、人事担当者も周りの教員も、即戦力としての活躍やある程度の社会人スキルを身につけていると期待をしているので、それが逆にプレッシャーになってしまうのです。
- 保護者対応ってどうやってやるの?
- 授業をもっと面白くするためには、どうしたらいいんだろう
- 会議も長いし、自分の業務をもっと効率的にするにはどうしよう
などなど、第二新卒と言っても、新卒教員と同じ悩みを持つのは当たり前です。
周りから「第二新卒だから、これくらいはできて当然」と新卒採用の教員よりも成果を求められることもあるのは、大きなデメリットになりますね。
第二新卒と言えど、新卒教員と同じような「素直さや謙虚な姿勢」を持つこと、また「これは得意だけど、これは初心者です」など、得意不得意を明確にして伝えておくと良いですね!
第二新卒に対する、人事のリアルな印象





第二新卒で教員をめざすことのメリットデメリットは分かったけど、実際の人事担当者の印象はどんな感じなの?
それでは、実際に第二新卒に対して学校人事が持つ印象を大公開していきます。
ポジティブな印象も懸念点もどちらもありますが、基本的には好印象を持っていることが多いですよ!
ポジティブな印象
メリットでもお伝えしましたが、学校人事担当者は第二新卒に対してポジティブな印象を持っていることが多いです。
- 社会人経験を通して、責任感や協調性といった社会人の基礎が身についている
- 必要最低限のビジネスマナーが身についている
- 新卒にはない、多様な視点や発想を教員として活かしてくれる
- 企業で培った経験を、学校運営や生徒指導に活かしてくれる
- 成長スピードが速い(だろう)
など、社会人経験をプラスに捉えて、それを教員として活かしてくれることに大きな期待をしています。
懸念点
一方で、第二新卒に対して(新卒と比べて)懸念に思う点ももちろんあります。
例えば
- 教員としての基本的な知識、スキルに不足がないか(大学で教職を学んでいたとしても、ブランクがあることへの懸念)
- 社会人経験があることがマイナスに働き、教員という働き方に馴染めないのではないか
- 教育現場特有の価値観への理解がスムーズにできるか
- 教員としてのキャリアパスのイメージが間違っていないか
- 前職の経験を教員として活かしきれるかどうか
- 教員の仕事に難しさを感じたら、また転職してしまうのではないか
といったところを特に心配しています。
一般企業と教員の働き方、キャリアパスの違いなどでのミスマッチを避けるために、教員採用試験を受ける際にはきちんと確認をしておくことが大切です。
>一般企業経験者に対して、教員採用面接で人事が確認する質問については、コチラの記事も参考にしてください▼
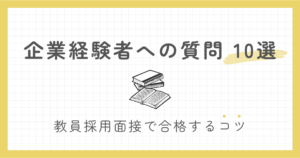
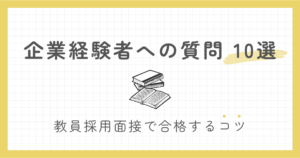
第二新卒の採用において重視するポイント



第二新卒の方の採用において、人事が特に重視しているポイントをご紹介します!
第二新卒の方の採用では、以下の5点をしっかりと確認するようにしています。
- 子どもたちへの愛情と教育への熱意
子どもたちの成長に根気強く寄り添い、教育という仕事に対して情熱を持っているかどうか。 - 経験からの学びと明確なビジョン
これまでの職務経験を通して何を学び、それを教員としてどうやって活かしていくのかが明確。 - コミュニケーションスキル
生徒、保護者、同僚との信頼関係を築き、うまくコミュニケーションが取れるか。 - チームワーク
教員はチームで働く組織です。周りの教員と協力し、取り組める姿勢があるか。 - 誠実さと責任感
教員として生徒を預かる責任感と、信頼を損ねることのない誠実さがあるか。
教員採用面接でもしっかりとチェックされているポイントですので、自分の長所と結びつけてアピールに使えると良いですね!



人事が心配している点をしっかりとクリアできるように準備して、面接対策しよう!
第二新卒で教員をめざすなら私立学校がオススメな理由
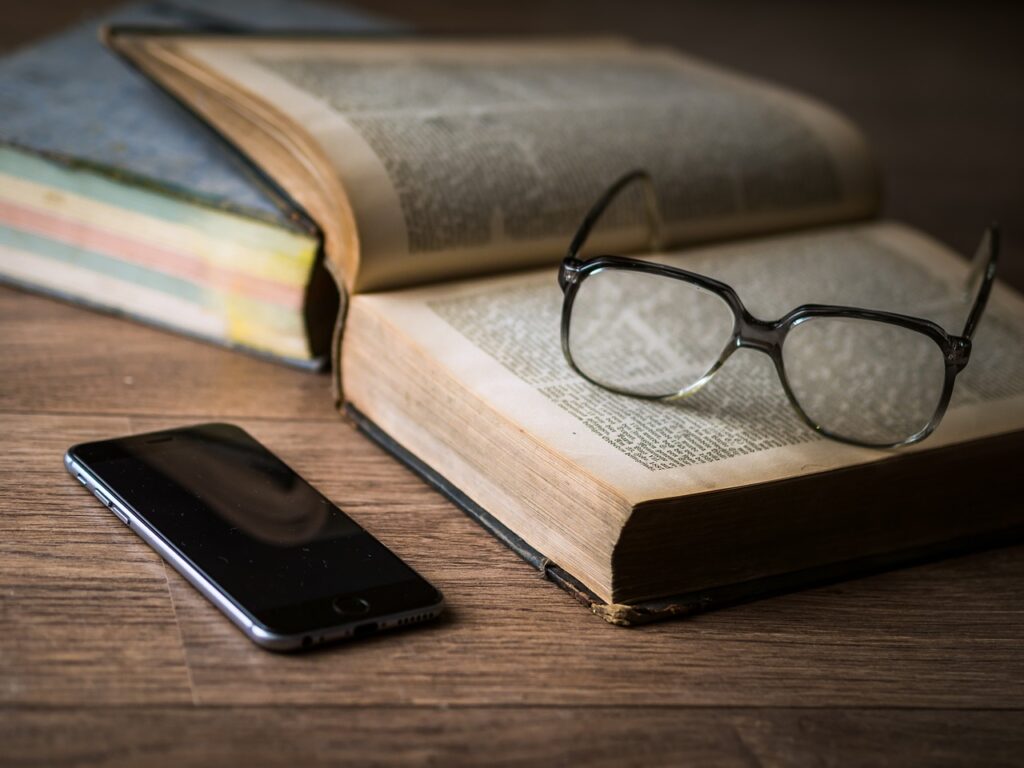
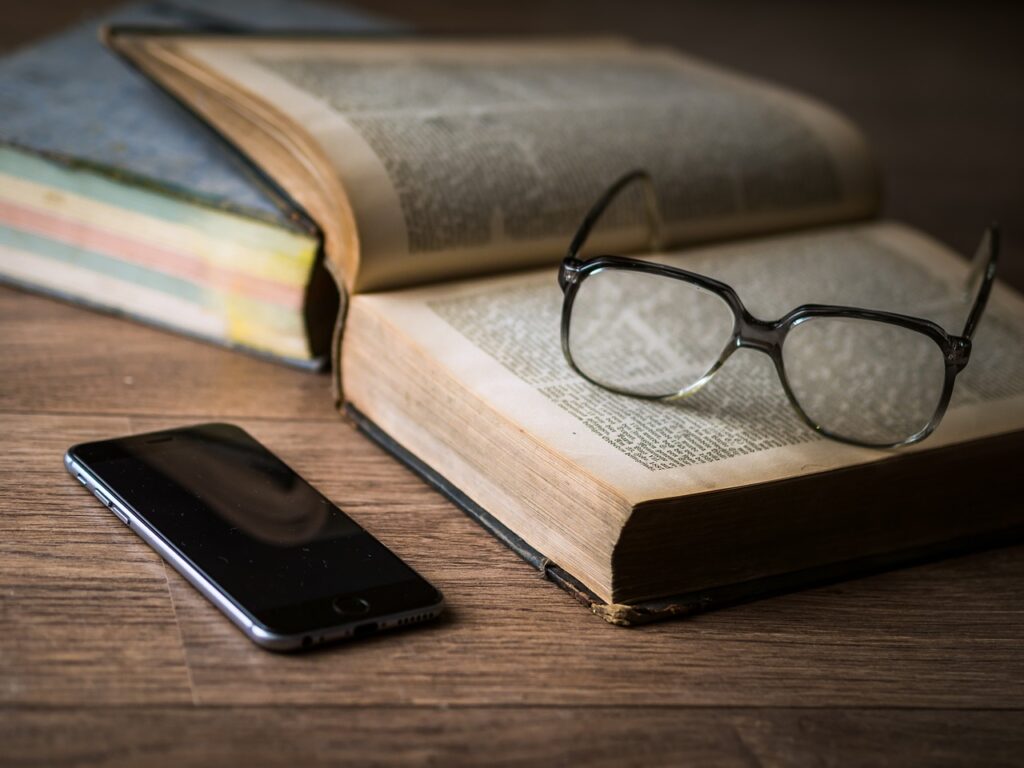
第二新卒で教員をめざしている方には、公立学校だけでなく私立学校も魅力的な選択肢となる可能性があります!
特に私立学校は、公立と比べて一般企業との共通点も多いので、「学校教育」という全く異なる世界であっても比較的馴染みやすい環境になると思います。
第二新卒で教員をめざす方に、私立学校がオススメの理由は以下の4つ。
- 一般企業との共通点が多く、馴染みやすい
- 採用面接で有利になる可能性が高い
- 私立学校そのものの魅力がある
- キャリアパスが豊富
1つずつ、具体的に見ていきましょう!
1.一般企業との共通点が多く、馴染みやすい
私立学校の運営体制や組織構造は、公立学校と比較して、一般企業に近い側面を持っています。
例えば
- 学校でありながら、経営意識がある(利益やコストの意識がある)
- 学校の特徴をとがらせるために、高い専門性を持つ人材が求められる
- さまざまなバックグラウンドを持つ人材を教員として受け入れる
- 仕事の頑張りや成果が評価される、成果主義の要素がある
というもの。
学校法人が運営する私立学校は、公立学校と異なり、生徒を募集して生徒の授業料で学校運営を行っており、その意味では一般企業の事業運営と同じです。
公務員として働く公立教員とは、また異なる感覚で教員という仕事ができるのが、私立学校です。
2.採用面接で有利になる可能性が高い
公立の教員採用試験は、年に1回、また筆記試験の結果や教科に対する専門知識などが重視される傾向にあります。
一方で、私立学校の教員採用試験は、学校ごとに採用スケジュールや選考方法が異なります。
複数の学校に応募することができたり、自分の経験や得意なことを活かして合格を狙うことができるのが、私立学校です。
3.私立学校そのものの魅力がある
文科省が示す学習指導要領に基づいて、一律の教育を行っている公立学校に対して、学校法人が運営する私立学校では、独自の教育方針を掲げて教育を行っています。
そのため、各学校独自の特徴を持っているのが普通で、独自のカリキュラムや最新の教育手法、ICT活用や少人数制などが導入されている学校もあります。
枠にとらわれない自由な発想の教育や、新しい教育にチャレンジしてみたい!と思って教員をめざす方には、私立学校の方がご自身の教育観にあった働き方ができるのが魅力になりますね!
4.キャリアパスが豊富
年功序列で教員経験を積み上げていくのが公立学校では一般的です。
それに比べて、私立学校では教員としての専門性を深めるだけでなく、さまざまなことにチャレンジしてキャリアを作っていくことができます。
例えば
- 管理職、マネジメントなどの責任者
- 部活動や進路指導など専門性を高める
- 経営や経理など、学校運営に携わる
- 新人育成や研修担当
- 広報人事、マーケティングなどのバックオフィス
などなど、教員として教壇に立ち続ける以外の役割が多くあり、興味関心に沿ってキャリアアップしていくことができる環境が整っています。



採用面接でも、教員以外の仕事の紹介やキャリアパスについても説明していますよ!
>教員をめざすなら読んでおきたい本をこちらにまとめています!ぜひ参考にしてください▼
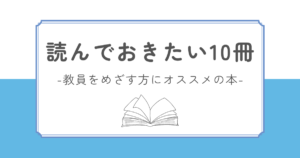
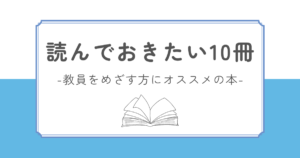
第二新卒を有利に使うために【エージェント利用もオススメ】


ここまで、第二新卒で教員をめざす方に向けてメリットデメリット、また私立学校がオススメな理由をご紹介してきました。



それでもやっぱり、教員になるって決めるのは不安‥どうしたらいいのかな。
実際自分にできるのかな?など、まだまだ不安に思われる方もいらっしゃると思います。
そんなときは思いきってエージェントに相談をしてみるのがオススメです。
一人でモヤモヤ悩んでいる間に、貴重な「第二新卒」の時期が過ぎて行ってしまいます!
- 無料で利用できる、相談に乗ってくれる
- 自分に合った転職先を見つけてくれる
- 一緒に転職活動を進めてくれる(書類や面接対策も)
- 最終的にまだ悩むのなら、転職しない!という道もアリ
ということで、まずは気軽に相談するイメージでエージェントを活用してみましょう。
20代に特化した転職エージェントUZUZでは、一人ひとりの経験や強みを引き出して、それを転職活動へ効果的に活かせるようサポートしてくれます。
【UZUZ第二新卒】民間から私立への転職が不安‥という方は、ぜひ気軽に登録してみてくださいね!
まとめ
今回は、第二新卒で教員をめざす方に、私立学校の人事担当目線でメリットとデメリットをご紹介してきました。
■メリット
- 企業での経験を活かして活躍できる
- 若さと吸収力があって、ポテンシャルが高い
- 新鮮な視点と意欲を持っている
■デメリット
- 教員採用試験合格のハードル
- 教員としてのキャリアパスの違いがネックになる
- 企業と学校の働き方のギャップに戸惑う
- 「第二新卒でしょ」という期待が大きい
メリットとデメリットを見ていろいろと感じることがあるかもしれませんが、一般企業での社会人経験は教員としてプラスになること間違いなしです!
少しでも「教員として働いてみたいな」と思っていらっしゃるのであれば、ぜひチャレンジしてみていただけるといいなと思います。
「自分らしく教員として働く」を実現させるために、少しでも参考になれば嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
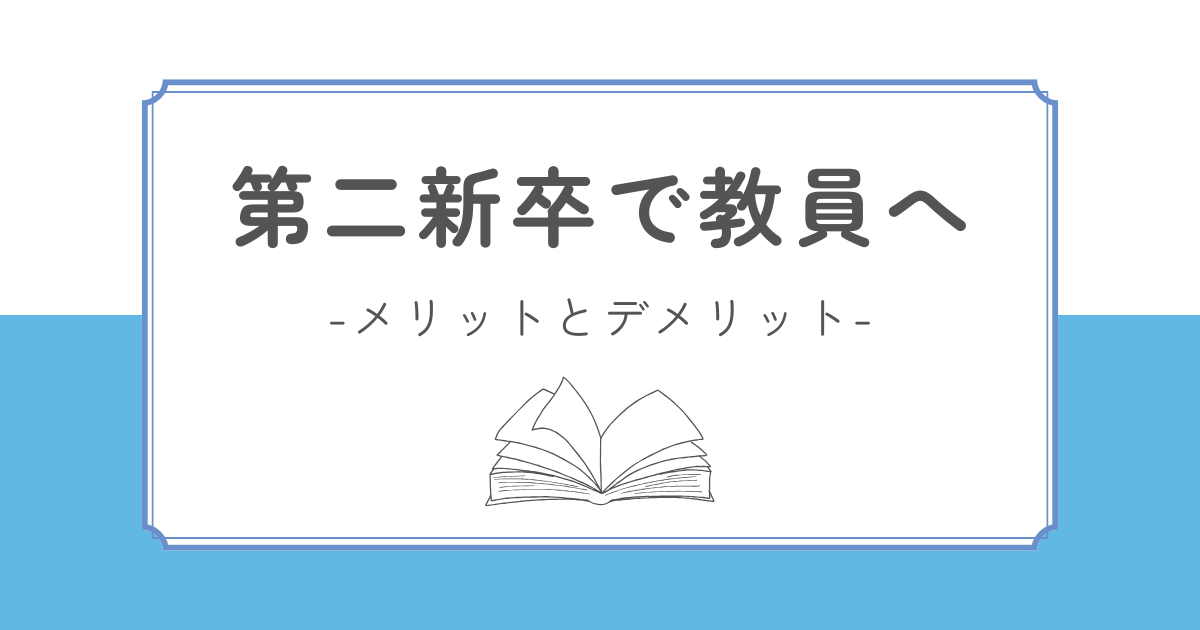
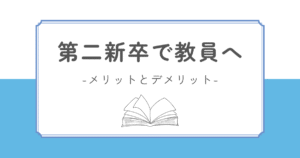
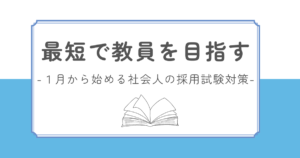
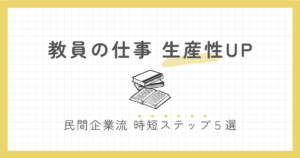
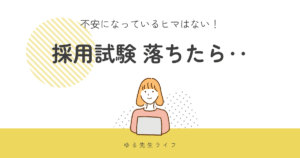
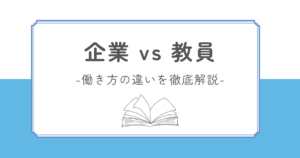
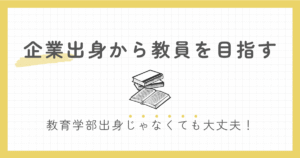
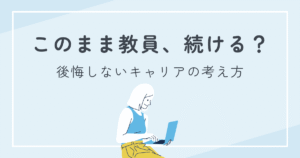
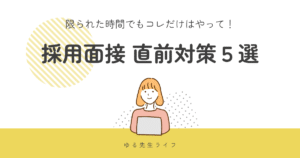
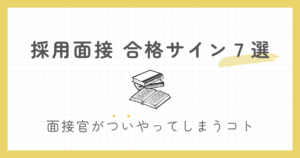
コメント