 教員志望の方
教員志望の方教員として働きたいと思っているけど、授業力を伸ばすにはどうしたらいいの?採用試験に模擬授業もあるし‥。



自分の授業に自信がなさすぎて‥どうしたらもっと生徒にとって良い授業になるんだろう?
教員をめざしている大学生のみなさん、あるいは転職しようとして教員採用試験を受けようと思っているみなさん、授業に対してこんな不安やお悩みはないですか?
「授業ってそもそも何をどうするの?」「経験積んだら上手くなるよ!って言われるけど、そんな無責任な‥」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
教員の大きな仕事の1つが、授業。1日の多くの時間を授業に使いますし、授業が楽しい先生は生徒からも人気です。
今回は「どうしたら自分の授業がもっと上手くなるだろう‥」とお悩みのみなさんに、私立学校での人事経験を基にオススメの本を10冊ご紹介します。
~自己紹介~
私は教員一家に生まれ、両親・叔父叔母・祖父はみんな公立小中高の先生。そして自身は英会話講師 → 私立高校で教員 → 今は教育関連企業で会社員しています。
教育業界で10年。そのうち8年間は人事を担当。教育業界での採用や転職に長く関わってきました。その経験をもとに、記事を書いています。
この記事を読むと
- 授業に求められているもの、教員に求められているものが分かる
- 自分の授業のレベルアップに読むべき本が分かる
- 自信を持って教員採用試験に臨めるようになる
- 本で得た知識を実践に移す方法が分かる
ぜひ最後まで読んでいただき、ご自身の授業のために参考になる本を選んでいただければ幸いです。
本を読むなら教員になる「前」がオススメ!
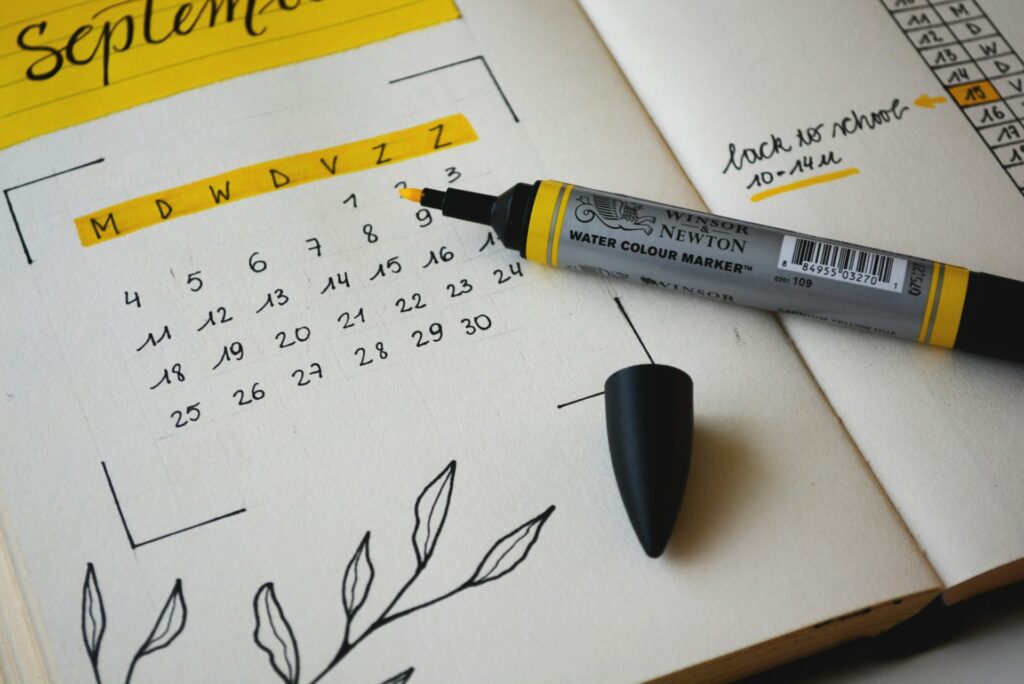
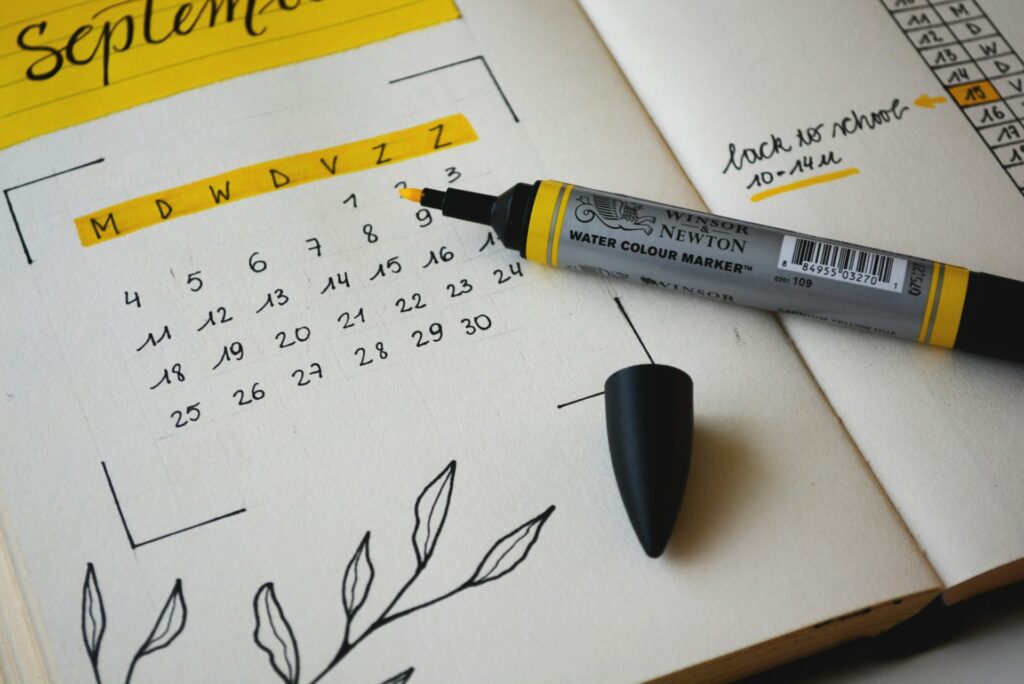
授業に関する本をご紹介していく前に、少しだけ。本を読むなら教員になる「前」が絶対良いです。
今まで採用担当として、いろんな方と関わらせていただきましたが
- 1年目の先生は、毎日の業務をこなしていくので必死(授業準備時間が取れないことが多い)
- 教員経験があっても、新しい職場に慣れるまで大変
ということで、働き出してからはなかなか腰を据えて授業のことを勉強する時間が取れないことが多いです。
また、教員採用試験で応募者とやり取りしていても
- 授業に対して自分で学んでいる姿勢は、好印象
ですので、就職活動中のすきま時間や、合格をもらって働き出す前までの時間を使って本を読むのをオススメします!



なかなか習慣にするのが難しい方でも、まずは1冊買って手元に置いておくことから始めてみてください。
【マインド編】授業に対する考えを深める4冊
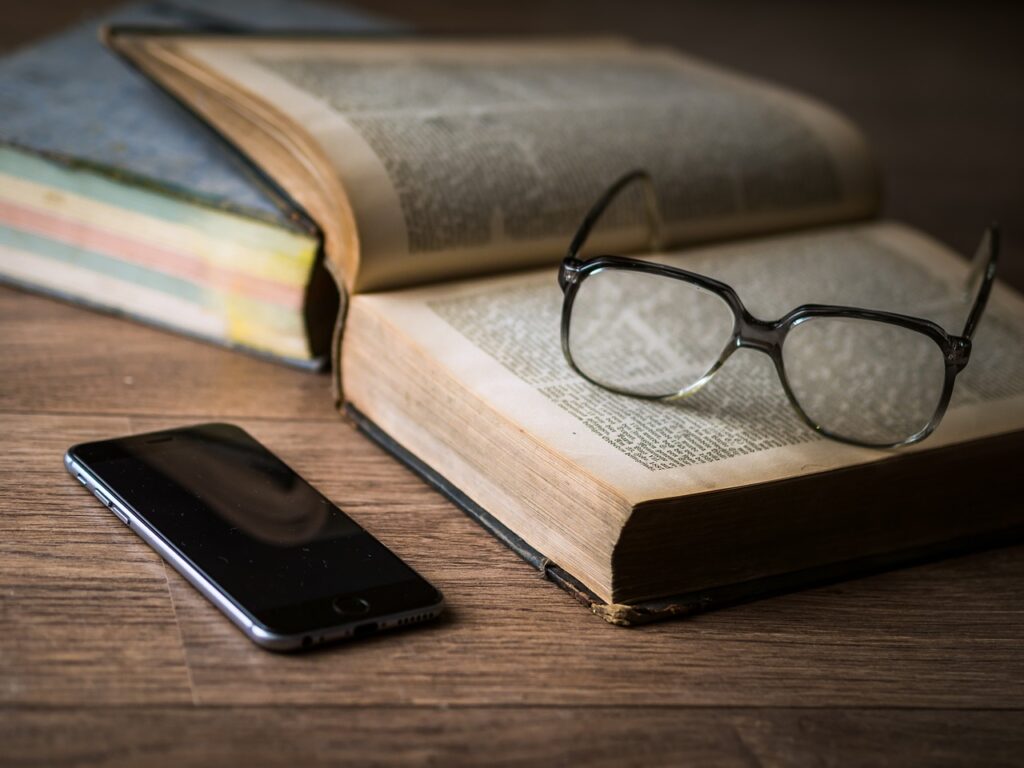
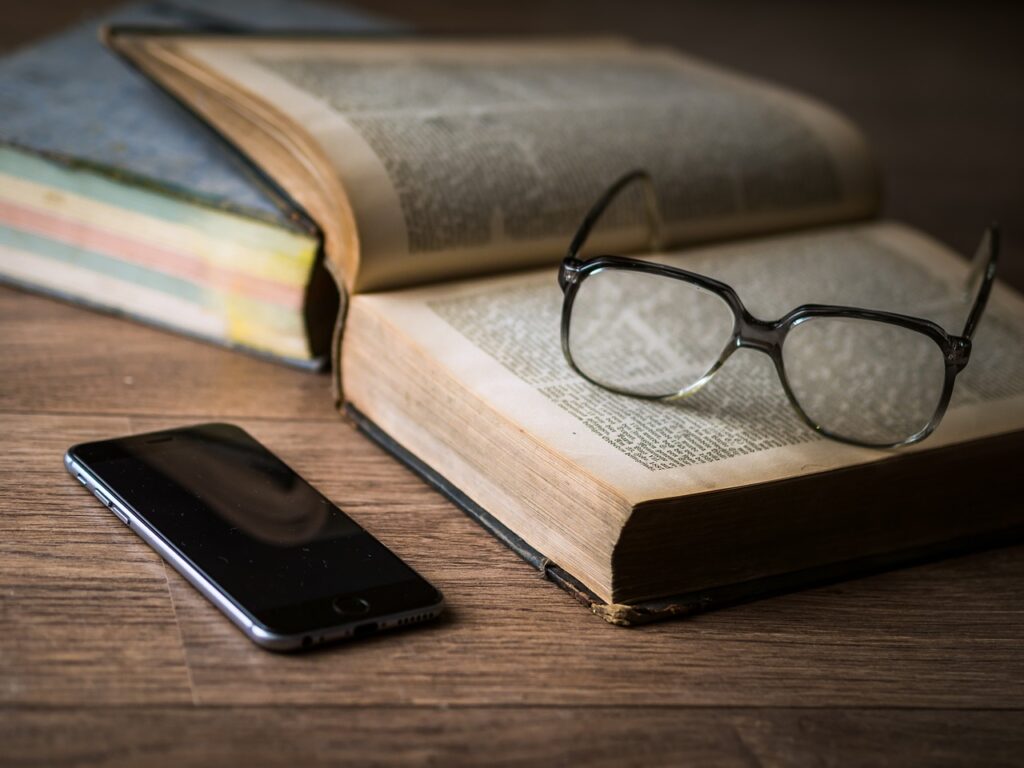
まずはじめに、授業とはどんなものか、時代に合った授業をするめにはなど、授業そのものに対する考え方を学べる本をご紹介します!
①学び方を学ぶ授業(難波駿)
令和時代の新しい授業のあり方を提案し、子どもたちが生涯にわたって使える「学ぶ力」を育むための具体的な行動が紹介されています。
知識伝達型の授業ではなく、子どもたちが主体的に学びに向かう授業を目指して「なぜ学ぶのか」「どのように学ぶのか」を子どもたちが考え、実践できるようなヒントが満載。
イマドキの授業に求められているものを理解したい、という方にはオススメの1冊。



「子どもたちが主体的に学ぶ授業」を実現したい、そんな方はぜひ読んでみてください。
②「生涯にわたって能動的に学び続ける力」を養う教科教育への挑戦(加固希支男)
「生涯にわたり学び続ける力をはぐくむことが必要」と文科省からも出されていますが、じゃぁ教科教育(授業)では実際どんなことができるのか、ということがまとめられた本。
算数科を具体例として、子どもたちが「生涯的に学び続ける力」をつけるためにできることが分かりやすく紹介されています。
授業ってどうあるべきか、なぜ教育教科が必要なのか、その中で教員がどう立ち居ふるまうかが分かる1冊。
算数・数学科以外の専門の方にも、教科を越えてオススメです。



授業を通してどんな子どもたちに育ってほしいかを教員が考え続けることが大切だと教えてくれる本です。
③揃わない前提の授業とクラス 授業づくりネットワーク
授業づくりネットワークが出している雑誌のNo.47。
「多様性」というと聞こえはいいものの、発達障害、ギフテッド、外国にルーツのある子‥いろんな子どもたちが過ごしている教室で授業をしていくのが現場の教員。
この号では、教室の多様性にどう対応していくべきなのかが具体的に紹介されています。
一斉・一律の授業をメインにやってきた今までの教育現場で、そもそも「揃わないことを前提として」授業やクラスを考えていく、という新しい視点が学べます。
「いろんな子がいると授業が不安」という方には、ぜひ読んでほしい1冊。



これからますます多様性が進んでいきます。みんなが心地よく過ごせる教室作りの参考になるはずです!
④失敗から学ぶ(石井英真)
授業に対して感じる不安は「失敗したらどうしよう」「うまく授業を成功させなきゃ」という気持ちが大きいのではないでしょうか。
でも、人は失敗して学んでいきます。
今ではベテラン教員として活躍されている先生方も、過去には失敗したことがたくさんあるのです。
そんな先輩教員の失敗経験から学びを得る、また自分の授業の失敗から次につなげるヒントを見つけることができるようになる1冊です。
授業に対しての不安や緊張が強い方には、頼れる味方になってくれること間違いなしです!



失敗するとどうしても凹んでしまいますが、「次はこうしてみよう!」と前向きな気持ちになれる、そんな本です。
【実践編】明日から使える実践スキル満載の6冊
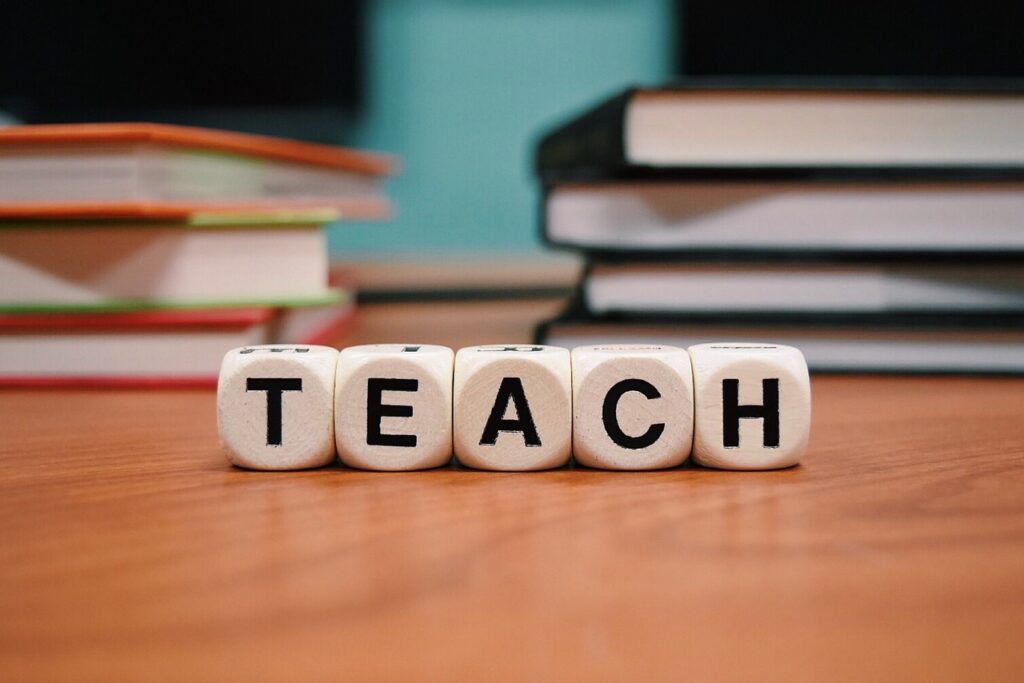
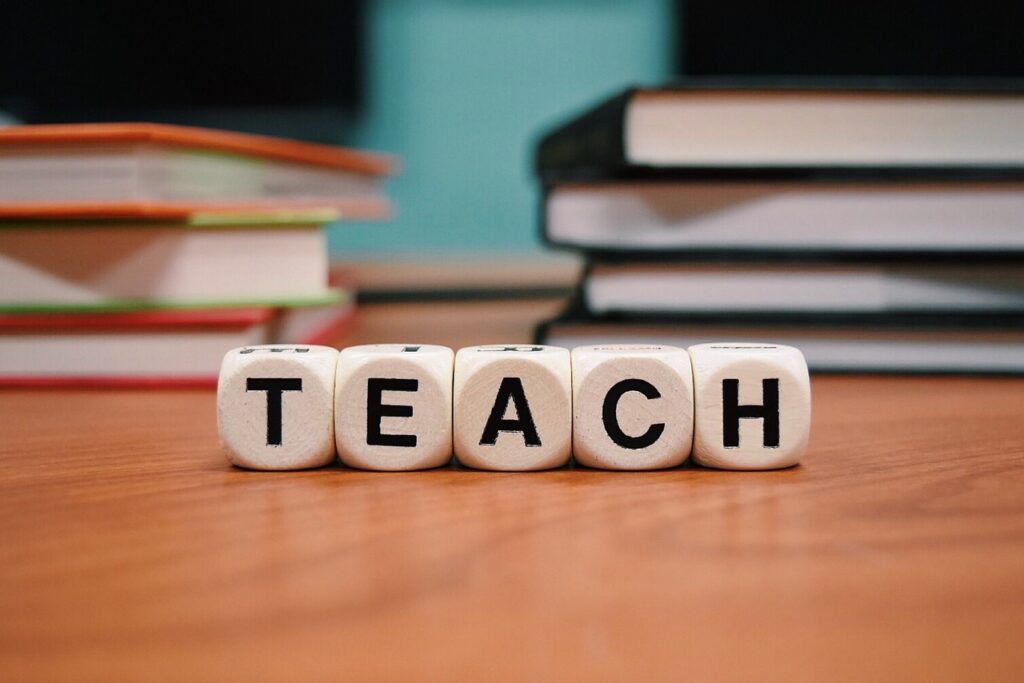
ここからは「実践編」ということで、授業中スグにに使える実践スキルがたくさん掲載されている本を紹介していきます。
模擬授業の対策としても、また自分の授業力をスグに上げたいという方に特にオススメの本です。
①授業の腕を上げる法則(向山洋一)
これから教員をめざす方が一番知りたいことは「授業って、何をどう、どんな順番で、どれくらいやったらいいのか」というところ。
そんな授業の【基礎基本】を丁寧に解説してくれている本です。
「探求学習」や「個別最適化」などと言われますが、そういった新しい教育を機能させるためのベースとなる一斉授業のやり方が分かります。
この本を読んで実践していくことで、教員としての基礎力が盤石になっていくでしょう。



新書なので持ち運びもしやすく、「教員の必携書」とも呼ばれている本。新人の先生たちには特にオススメしています。
②図解で詳しく分かる先生1年目からの授業づくり完全ガイド(浦元康)
タイトルの通り、1年目の先生が自信を持って授業づくりに取り組むための実践的なガイドブックです。
授業の基本の流れから、年間指導計画の立て方、教材研究、発問、板書、グループワーク、評価方法、保護者対応まで、授業に関わるさまざまな場面が図解とイラストで分かりやすく解説されています。
1年目の新任の先生はもちろん、教員をめざしている大学生の方、合格をもらって次年度から教員になる方には絶対に読んでおいてほしい1冊です。



図解で説明してあるので、教室での実際の動き方がイメージできて分かりやすい!
③授業の腕をあげる ちょこっと「全教科」スキル(高橋朋彦)
この本では小学校の先生に向けて、日々の授業をちょっとした工夫で面白く、分かりやすくするためのアイディアが全教科横断的に紹介されています。
教科書の見方や発問の仕方、ノート指導、グループワーク、振り返りの方法など具体的な場面で使えるスキルが分かりやすく解説されています。
「授業」に対する普遍的なスキルが紹介されていたり、授業を活性化させるヒントが載っているので、中学高校の先生にもオススメの1冊です。



生徒の年齢に応じて少しアレンジが必要ですが、本質的なところはどの学校の先生にも通じます!
④授業がうまい教師のすごいコミュニケーション術(菊池省三)
生徒たちの学びを深める、よりよい授業をしていくために必要な教員のコミュニケーションスキルについて書かれた本です。
授業中の言葉遣い、表情、声のトーンといった非言語コミュニケーションから、効果的な発問方法、しかり方・褒め方、傾聴の姿勢など、直接的なコミュニケーションスキルまで、具体例を出しながら説明されています。
やるべきことを淡々と進めるだけが授業ではありません(そんな授業はAIでもできてしまいます)。
生徒にとっての「安心感」にもつながる教室でのコミュニケーションスキル、一度読んでおくことをオススメします。



生徒とのコミュニケーションに悩んでいる方にもオススメの1冊です。
⑤ここだけはおさえたい!教師1年目の授業づくり(野中信行)
この本は、1年目の先生が授業づくりで「ここだけは絶対に押さえておきたい!」という最重要ポイントに絞った実践的なノウハウが紹介されている本です。
何を準備するの?どうやって始めて、次に何をするの?どうやって終えればいいの?と、なぁなぁになりそうな部分に対してもシンプルで分かりやすい言葉で説明してくれています。
小学校での授業をベースに書かれていますが、授業づくりの心構えや失敗例成功例、生徒対応例など、どの学齢でも必要な知識がつまった1冊。



あれもこれも!やらなきゃ!!とプレッシャーに感じてしまう方は、まずはこれ1冊を参考にやってみるのもオススメです。
⑥続ければ本物になる 帯指導の教科書(山﨑克洋)
この本は、小学校での帯指導(時間割の隙間などを活用して行う指導)に焦点を当てた実践的な教科書で、小学校と言いながらも、中学校でも十分使える内容になっています。
ともすれば過ぎ去っていくだけの帯の時間を、いかに目的意識を持って取り組むかで子どもたちの成長度合いが変わってきます。
具体的な帯指導のアイディアと、その効果を高めるための考え方が詳細に紹介されていますよ!
授業の効果をさらにUPさせるためにも、プラスアルファで読んでおきたい1冊です。



学校生活はルーティンで成り立っています。毎日のちょっとしたプラスが1年後には大きな成長につながっていきます!
以上、授業に関するオススメの本10冊をご紹介してきました。
>また授業以外でも「教員をめざす方に読んでおいてほしい本」もご紹介していますので、コチラの記事もぜひ読んでみてください!
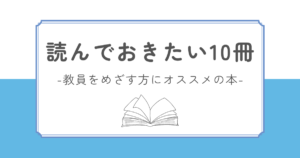
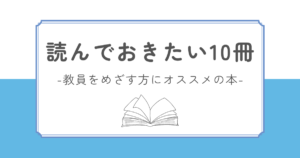
本で得た知識を実践に活かす方法


せっかく忙しい中本を読んで知識を身につけても、知識のまま持っておくだけではもったいないですよね。
実際によりよい授業にするためには、「意識的な実践と振り返り」が不可欠です。
ここでは、本で得た知識を明日からの授業で活かし、生徒の主体性を引き出すためのステップをご紹介していきます!
知識を実践に活かす具体的な5ステップ
本を読んで知識が増えると、あれもこれもやりたい!という気持ちになりますよね(←私のことです笑)。ただ、一度に多くのことをやろうとしても、結局中途半端になるだけです。
まずは「これなら簡単にやれそう」「ちょっと面白そう」と感じたアイディアを1つだけ選んで、これをやろう!というのを決めます。
やってみようと決めたアイディアを、いつ、どの授業でどのように実践するのかを具体的な計画を立てます。
対象学年・教科・単元、授業のどのタイミングで、どのようにやるか、計画を立てることでイメージが湧き、実施しやすくなります。
また、後で振り返りしやすくなるので、計画を目に見える形で残しておくこともオススメです。
計画に基づき、実際にアイディアを実践してみましょう。最初は手間取るかもしれませんが、「ちょっとやってみる」くらいの気持ちで臨むと良いです。
実際に授業で取り入れたときに
- 生徒は興味を持っているか?
- 発言は活発になったか?
- 理解度は深まったか?
- 予想外の反応はあったか?
などを、注意深く観察してメモをしておきましょう!
授業後に、実施したアイディアについて必ず振り返りを行いましょう。
- 計画通りに実施できたか、ねらい通りに効果があったか
- 生徒の反応はどうだったか
- 上手くいった点と改善点は?
もし可能なら、同僚の先生に授業を見てもらって客観的な意見を聞くのも有効です。
教員採用試験(模擬授業)前の方であれば、友人や大学の先生に協力してもらうのも良いでしょう。
一度試して終わりではなく、振り返りで気づいたことをもとに、改善を加えて再度同じアイディアを別の授業で試してみることが大切です。
例えば、発問の仕方が分かりにくかったのであれば、より具体的な指示を加えてみる、グループワークが上手くいかなかったなら、人数や課題を調整してみる、など。
そのたびに、②~④を繰り返して、よりよくできるようにしていきます。
この5つのステップを繰り返していくことで、本で得た知識を自分のものとして、授業で活かしていくことができるようになります!
学び続ける姿勢を持つことは大切
授業改善に、終わりはありません。
「もっと良い方法はないかな」「生徒にとって学びやすい授業とは?」という問いを持ち続け、積極的に新しい知識や情報を取り入れる姿勢が大切です。
また、教員採用試験でも「向学心」「学び続ける姿勢」がプラスに評価されることが多いです。
ぜひ自分の教員としての成長も感じながら、楽しく取り組んでみてください!



授業は生徒と一番多くの時間を過ごす時間。授業に対する熱量が高い先生は、学校にとっても貴重な人材になります。
まとめ
今回は、授業に対して不安を持っている先生方や大学生の方に向けた、オススメの本10冊をご紹介しました。
教員として働いてく上で、授業というものは切っても切り離せない、生徒にとっても教員にとっても大切な時間です。
すでに教員として働いている方も、これから教員をめざす方ならなおさら、よりよい授業を目指してぜひ参考にしてみてください。
良くも悪くも生徒からダイレクトに反応が見れるのも、おもしろいポイントですね。応援しています!
以上、参考になれば嬉しいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
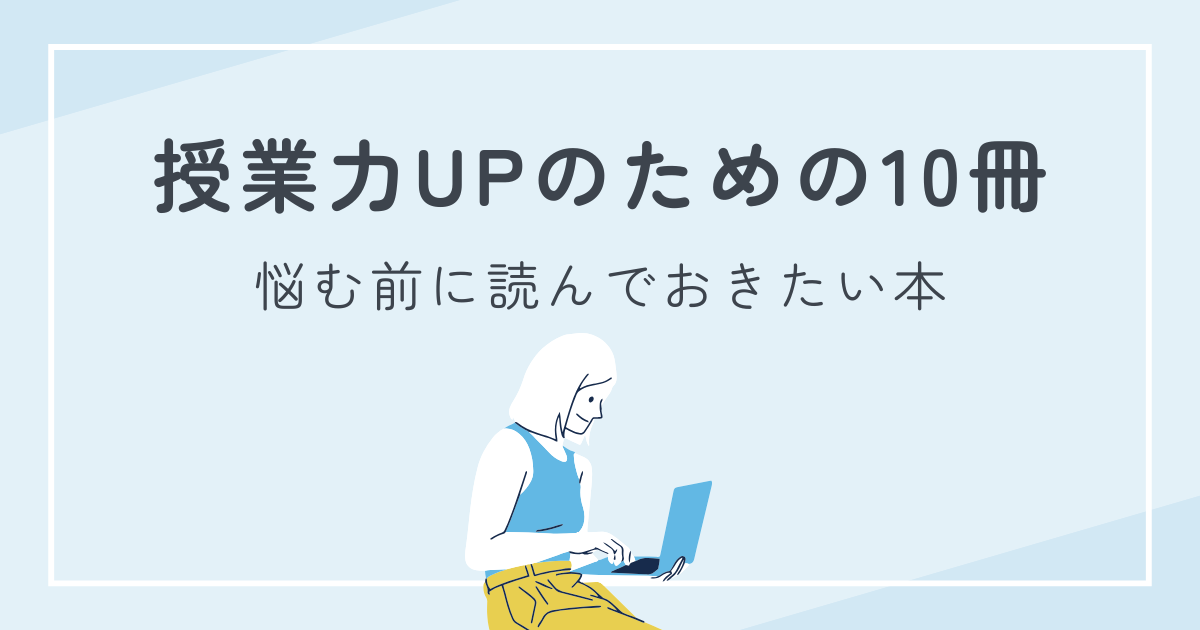
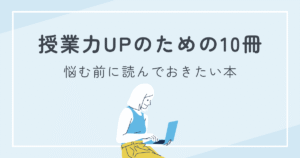
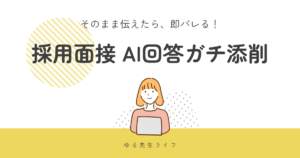
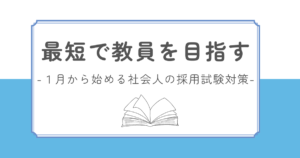
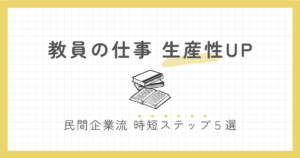
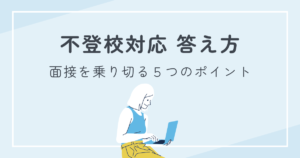
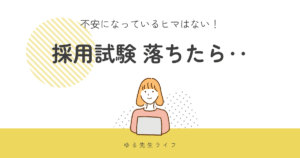
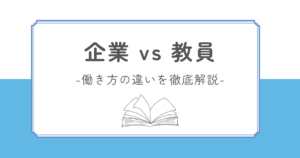
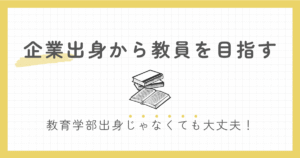
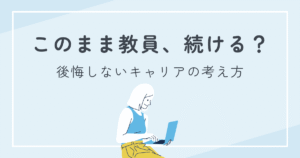
コメント